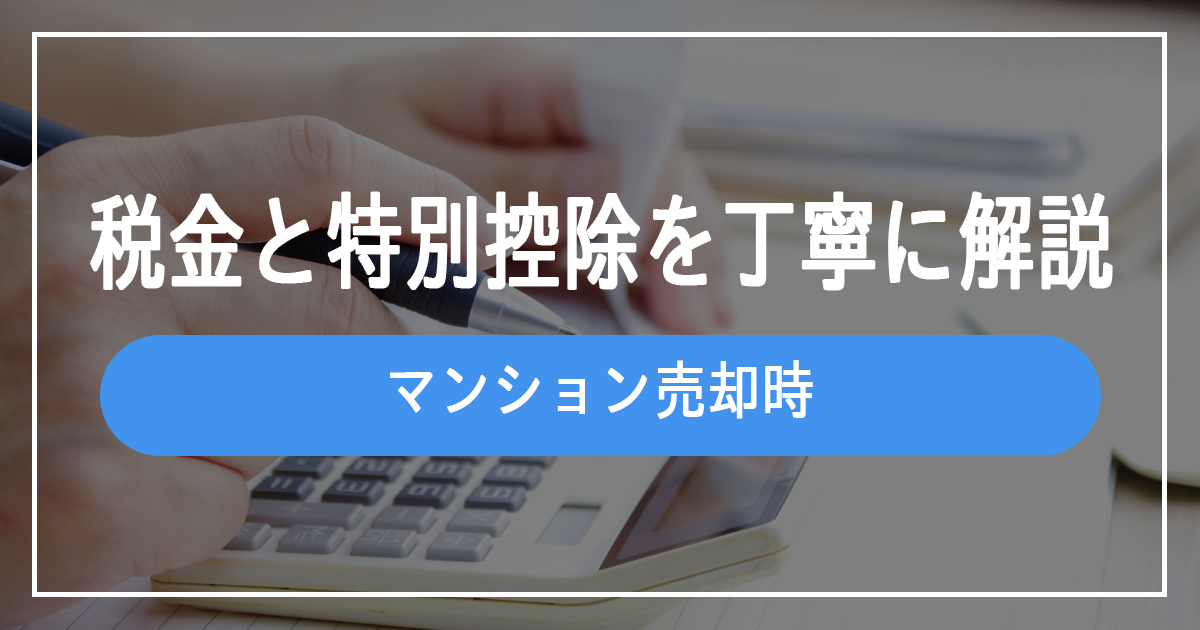マンション売却で利益が出た場合、その利益を譲渡所得として確定申告し「所得税」「住民税」を支払いが必要です。
しかし、この税金に関しては控除が設けられており、支払いが必要ないケースもありますし、支払いが必要でも特例を使えば減額できます。
その他にも「印紙税」や「登録免許税」など必須の税金もあるのでしっかりと把握し事前にある程度の税額を押さえましょう。
1. 譲渡所得税
マンションを売却して、利益が出た場合にのみ、譲渡所得として「所得税」と「住民税」が課税さてます。
簡単に言えば、3000万円の物件を購入し、4000万円で売れた場合、1000万円の利益が出ていると見なされ、1000万円の部分に税金が掛かってきます。
しかし、実際は購入価格より売却価格が高くなる中古マンションはそんなにありませんし、仮に高く売れたとしても、一定の要件(後述します)を満たしている中古マンションには3000万円の特別控除が適用されるのでほとんどの方は利益が出ません。
- マンションの売却価格が購入価格より安い
- 利益は出そうだけど3000万円以下
という方は非課税なので安心してください。
ただし、これは確定申告しなくていいというわけではありません。
利益が出ていなくても、確定申告することで所得税の還付が受けられますし、3000万円の特別控除も確定申告しなければ受けることができません。不動産売却後は必ず確定申告をしましょう。
譲渡所得税の計算方法は以下の通りです。
1-1. ①まずは譲渡所得を計算
譲渡所得=売却価格―[(取得費―減価償却費)+譲渡費]
- 譲渡所得
マンションを売って出た利益 - 取得費
取得費は、売却するマンションを購入した時にかかった費用から、建物の減価償却分を差し引いた金額となります。取得費には物件購入価格以外に購入時時に支払った仲介手数料や登記費用があればそれを含めることもできます。契約書で取得費を調べる時は税抜価格なのか税込価格なのか確認しておきましょう。なお、取得費が分からない場合には売却価格の5%を概算価格として算出することができます。また、取得費に関しては、減価償却費分を差し引いて計算する必要があります。 - 譲渡費
譲渡費は、売却のために直接支払った費用のことで、売却のために支払った仲介手数料や登記費用、測量費用などが含まれます。 - 減価償却費
マンションは老朽化によって年々、資産価値は減少していきます。
この資産価値が減った分を「減価償却費」と言います。
減価償却費の計算方法
減価償却費=建物購入代金 × 0.9 × 償却率 × 経過年数
・建物購入代金・・・土地は老朽化するわけではないので、あくまで建物部分のみ。契約書を確認してみましょう。
・0.9・・・どんなに古くなっても多少価値がある(残存価格)と考えられ、10%とされているため。
・経過年数・・・6ヶ月未満は切り捨て、6ヶ月以上は1年。
・償却率
| 耐用年数 | 償却率 | |
| 木造 | 33年 | 0.031 |
| 軽量鉄骨 | 40年 | 0.025 |
| 鉄筋コンクリート造 | 70年 | 0.015 |
多くのマンションは鉄筋コンクリート造なので法定耐用年数70年(70年で資産価値0)の償却率0.015となる。
1-2. ②次に特別控除3000万円を差し引く
譲渡所得から3000万円の特別控除分を差し引くことで課税対象になる金額が出ます。
| 実際に課税させる分(課税譲渡所得)=譲渡所得―特別控除(3000万円) |
1-2-1. 居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例(措法35条)
この特例は、マンションを売って譲渡所得が生じた場合でも、3000万円が控除される制度です。つまり譲渡所得が3000万円以下であれば「所得税」「住民税」は課税されないことになります。
1-2-2. 3000万円の特別控除適用条件
- 居住用として利用していた。(別荘、建て替え時の仮住まい、実際には住んでいないけど住民票の住所だけある、なとは対象外)
- 親子や夫婦など、一定の特別関係への売却でないこと。
- 住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却すること。
- 「10年超所有軽減税率の特例(a.)」との併用は可能だが、「特定の居住用財産の買換えの特例(b.)」との併用は不可。
- 売却した年の「前年」及び「前々年」にこの特例、又は「特定の居住用財産の買換えの特例(b.)」や「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(c.)」若しくは、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(d.)」の適用を受けていないこと。
(a.)10年超所有軽減税率の特例(マイホームを売ったときの軽減税率の特例)-措法31-
(国税庁HP参照:https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3305.htm)
譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合、3000万円の特別控除に加え、特別控除後の譲渡益にているつに課税が行われます。(3000万円控除と併せて利用できるので後述)
(b.)特定の居住用財産の買換えの特例(特定のマイホームを買い換えたときの特例)-措法36の2-
(国税庁HP参照:https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3355.htm)
所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡し譲渡益が発生しても、一定期間内(居住用財産を売却した年の前年から翌年までの3年の間)に新たな居住用財産を取得すれば、本来かかる税金を新たな居住用財産を売却するまで繰り延べできるという制度。
ただし、「譲渡代金」と『買換え代金』を比較し、『買換え代金』の方が大きければ譲渡益への課税は繰り延べられますが、「譲渡代金」の方が大きい場合には「買換え代金」充当分への課税は繰越し、差額分には長期譲渡所得として課税されます。
この特例は、あくまで税金を繰り延べできるというもので、非課税になりわけではないので注意が必要です。
(c.)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)-措法41の5-
(国税庁HP参照:https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm)
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」マンションなどの居住用財産(旧)を売って、一定の期間中(居住用財産を売却した年の前年から翌年までの3年の間)に、新しいマンションや戸建などの居住用財産(新)を購入した場合に、旧居住用財産の売却に関して損失が出た時は、一定の要件を満たせば。その損失をその年の他の所得(給料、退職金、配当金など)から控除(損益通算)することができます。さらに損益通算しても控除しきれなかった損失は、売却の翌年以降3年以内であれば繰り越して控除することもできます。
(d.)特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)-措法41の5の2-
(国税庁HP参照:https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm)
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」住宅ローンの残っているマンションなどの居住用財産を、住宅ローン残高を下回る金額で売却し損失が発生したとき、定められた要件を満たしていれば、その損失をその年の他の所得(給料、退職金、配当金など)から控除(損益通算)することができます。さらに損益通算しても控除しきれなかった損失は、売却の翌年以降3年以内であれば繰り越して控除することもできます。
この特例では、上述した(c.)のように新しいマンションや戸建てを購入しない場合であっても適用可能です。
また、住宅ローンの残高から売却金額を差し引いた残りの金額が、損益通算の限度額となになります。
ただし、損益通算・繰越控除の対象金額は、
①、(取得費+譲渡日)-売却金額
②、ローン残高-売却金額
この2つのうち金額の少ない方になります。
- マンションなどの居住用財産売った年と前後の2年ずつの5年間に住宅ローン控除を受けていない。
住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
(国税庁HP参照:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm「35条」)
(国税庁HP参照:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm「35条」)
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、10年以上の返済期間のある住宅ローンを利用して、マンションなどの居住用財産を購入した場合、10年間、年末における住宅ローン残高の1%を、毎年支払う「所得税」「住民税」から控除してくれる制度です。つまり給与所得者などは確定申告することで「所得税」や「住民税」が還ってくるということになる。
1-3. ③最後に譲渡所得税を計算
譲渡所得から特別控除を引いたら、実際の譲渡所得税を計算します。
所有期間によって「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分けられ、それぞれ定められた税率を乗じて計算します。
所有期間の判定は、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下か5年超で判断する。
また、所有期間が10年を超える場合には3000万特別控除と併せて、長期譲渡所得の課税の特例を使い税率を軽減できます。
| 所有期間 | 区分 | 税金 |
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 譲渡所得×39.63%
(所得税30.63%、住民税9%) |
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 譲渡所得税×20.315%
(所得税15.315%、住民税5%) |
| 10年超所有軽減税率の特例 | 長期譲渡所得 | ①課税譲渡所得6,000万円以下の部分×14.21%
(所得税10.21%・住民税4%) ②課税譲渡所得6,000万円超の部分×20.315% (所得税15.315%・住民税5%) |
2. 印紙税
マンションを売却する際には不動産売買契約書を締結することになり、不動産売買契約書に印紙を張ることで印紙税を払います。ちなみに実際に印紙を購入するのは不動産会社なので、売主は該当金額を用意していくことになります。
※不動産の売買に関する契約書にかかる印紙税は、平成30年3月31日までの間であれば軽減税率の適用を受けることができます。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 10万を超え 50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え 100万円以下 | 1千円 | 500円 |
| 100万円を超え 500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
| 500万円を超え 1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円を超え 5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円を超え 1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え 5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円を超え 10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円を超え 50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
3. 司法書士への報酬(登記費用)
不動産登記とは「誰が所有しているのか?」「どんな権利がついているのか?」を法務局管理の登記簿に記載することです。
マンション売ることで登記内容があなたから第三者に変更になるわけですから、登記の変更が必要です。
マンション売却では「決済・引渡し」の日に司法書士も呼んで(1.)所有権移転登記を行います。場合によっては(2.)(3.)も必要です。
- 所有権移転登記・・・マンションの所有権を移転する。
- 抵当権抹消登記・・・売主が銀行からローンを借りている抵当権を消す。(すでにローン完済がされていて抵当権抹消登記が終っていれば必要なし。)
- 住所変更登記・・・売主がすでに新居で生活していて住民票は移していても、登記簿に記載されている住所も自動的に変更になるわけではありませんので、別に変更登記が必要です。(登記簿上の住所と、印鑑証明書の住所が一致していれば必要なし。例えば・・・?)
3-1-1. 登記費用はどっちが負担するの?
所有権の移転登記は買主が負担し、抵当権抹消登記や住所変更登記も必要があれば売主がその部分を負担します。
3-1-2. 司法書士はどうやって探すの?
メインである所有権移転登記を買主が負担するので、買主が選ぶことになります。そして売主側に抵当権抹消登記や住所変更登記が必要であれば、買主さんが選んだ司法書士に一緒にお願いします。
ちなみに買主に頼みたい司法書士(知り合いなど)がいなければ、不動産会社が紹介するのが普通です。
3-1-3. 登記費用の値段はいくら?
登記手続きにあたり、司法書士に支払う費用は「登録免許税」と「司法書士報酬」の2つに分けられます。
- 登録免許税・・・登記の申請を行う際に国に払う税金。マンションの固定資産税評価額によって必要な額が異なります。
| 通常 | 一般住宅特例 | 長期優良住宅特例 | |
| 所有権移転登記 | 2.0% | 0.3 | 0.1 |
| 抵当権抹消登記 | 不動産1個につき1000円(土地で1個、土地で1個と数え、マンションにも土地部の割り当てがあるので×2で計算※複数の土地にまたがっている場合はその分も数えます) | ||
| 住所変更登記 | 同上 | ||
一般住宅特例は、自己居住用の住宅で、取得後1年以内に登記、築20年(耐火建築物の場合築25年)以内、床面積50㎡以上といった条件を満たすことで適用を受けることができます。
例えば、建物の評価2,000万円のマンションの売却であれば、2,000万円×0.3%で登録免許税6万円を買主は支払う必要があります。
- 司法書士報酬・・・売主が負担するのは、「抵当権抹消登記」と「住所変更登記」に関わる司法書士報酬です。地域や司法書士事務所によって異なりますが2~3万程度と登記費用の数千円が相場です。
4. まとめ
今回は、マンション売却に関係する税金の基本を説明しました。しかし、税制は頻繁に改正が行われます。不動産会社の担当者、もしくは税理士に必ず確認しましょう。最近は税務署も丁寧に教えてくれるので積極的に利用してみましょう。